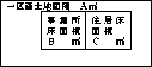○伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年11月1日
条例第177号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者」という。)と土地所有者との協議が成立したときは、当該権利者を受益者とする。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表のとおりとする。
(賦課対象区域の決定)
第5条 管理者は、毎年12月に、翌年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。賦課対象区域は、公告の日の属する年の翌年度内に供用開始することが予定されている区域とする。ただし、管理者は、賦課対象区域を変更する必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 管理者は、前項ただし書の規定による賦課対象区域を変更したときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 受益者が公の生活扶助を受けているとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(令2条例38・一部改正)
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 受益者は、第6条第3項の納期限後にその負担金を納付する場合においては、当該負担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を加算して納付しなければならない。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。
5 延滞金の額を計算する場合において、第1項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(督促)
第11条 管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者に対し、期限を指定して督促しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年伊勢市条例第26号)、二見町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年二見町条例第20号)、小俣町下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年小俣町条例第17号)又は御薗村公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年御薗村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(令2条例43・一部改正)
附則(平成18年9月29日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第5項、第3条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第5条、第4条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第5条の規定による改正後の伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第4項、第6条の規定による改正後の伊勢市道路占用料徴収条例第6条、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項並びに第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年10月10日条例第31号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日条例第38号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例附則第4項、第4条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第4条、第6条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令2条例38・一部改正)
1 合併前の伊勢市の区域(5の表に定める区域を除く。)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 負担金の額 |
宇治中村負担区 | 508円 | 当該受益者が基準日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、第5条の規定により公告された区域内に存するものの面積に左記の負担区ごとに1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額。ただし、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。 |
いせ第1負担区 | 508円 | |
いせ第2負担区 | 508円 | |
いせ第3負担区 | 508円 | |
いせ第4負担区 | 508円 |
2 合併前の二見町の区域(5の表に定める区域を除く。)
負担金の額 |
一般家庭1件につき150,000円。ただし、事業所等にあっては、管理者が別に定める。 |
3 合併前の小俣町の区域(5の表に定める区域を除く。)
負担金の額 | |||
1戸割80,000円(ただし、第3条第2項の規定による排水区域の公告前の区域については、「20,000円」と読み替え算定する。) *独立して生活を営む世帯、共同住宅等は居住世帯ごととする。 | |||
戸割額に、次の金額を加算する。 (1) 飲食店 旅館 | |||
| 店舗面積 | 50m2未満 | 20,000円 |
〃 | 50m2以上100m2未満 | 25,000円 | |
〃 | 100m2以上200m2未満 | 45,000円 | |
〃 | 200m2以上 | 65,000円 | |
*ただし、喫茶店、スナック等は1店舗につき15,000円加算する。 (2) 食品製造業・卸し業 | |||
| 従業員 | 5人以下 | 50,000円 |
〃 | 6人以上10人以下 | 100,000円 | |
〃 | 11人以上15人以下 | 150,000円 | |
〃 | 16人以上20人以下 | 200,000円 | |
〃 | 21人以上 | 250,000円 | |
(3) 理容院 美容院 戸割 25,000円 (4) クリーニング店 戸割 30,000円 (5) 医院 戸割 60,000円 (6) 商店(食品販売業)その他事業所等 | |||
| 店舗面積 | 50m2未満 | 20,000円 |
〃 | 50m2以上100m2未満 | 30,000円 | |
〃 | 100m2以上200m2未満 | 60,000円 | |
〃 | 200m2以上300m2未満 | 100,000円 | |
〃 | 300m2以上400m2未満 | 150,000円 | |
〃 | 400m2以上500m2未満 | 200,000円 | |
〃 | 500m2以上700m2未満 | 300,000円 | |
〃 | 700m2以上 | 400,000円 | |
*ただし、その他事業所とは、従業員5人以上を対象とする。 (7) 公共施設等 | |||
| 建築面積 | 50m2未満 | 20,000円 |
〃 | 50m2以上100m2未満 | 30,000円 | |
〃 | 100m2以上200m2未満 | 60,000円 | |
〃 | 200m2以上300m2未満 | 100,000円 | |
〃 | 300m2以上400m2未満 | 150,000円 | |
〃 | 400m2以上500m2未満 | 200,000円 | |
〃 | 500m2以上700m2未満 | 300,000円 | |
〃 | 700m2以上 | 400,000円 | |
4 合併前の御薗村の区域(5の表に定める区域を除く。)
①一画地の用途 | ②一画地の土地面積(m2) | ③算定額 | ④追加公共ます単価 | ||||
面積要件 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | |||
専用住宅 |
| 80,000円 |
| 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
事業所 | A≦300m2 | 100,000円 |
| 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
300m2<A | (A-300m2)×300円+100,000円 | A≦600m2 | 80,000円。ただし、③+80,000円>190,000円のときは③に加算した額が190,000円になる額。 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
600m2<A≦900m2 | 0円 | 80,000円。ただし、③+80,000円>280,000円のときは③に加算した額が280,000円になる額。 | 80,000円 | 80,000円 | |||
900m2<A≦1,200m2 | 0円 | 0円 | 80,000円。ただし、③+80,000円>370,000円のときは③に加算した額が370,000円になる額。 | 80,000円 | |||
1,200m2<A | 0円 | 0円 | 0円 | 80,000円。ただし、③+80,000円>460,000円のときは③に加算した額が460,000円になる額。 | |||
住宅及び事業所 | A≦300m2 | 100,000円x+80,000円y |
| 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
300m2<A | 10,000円x+300円Ax+80,000円y | Ax≦300m2 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
300m2<Ax≦600m2 | 80,000円。ただし、(Ax-300m2)×300円+100,000円+80,000円>190,000円のときは(Ax-300m2)×300円+100,000円に加算した額が190,000円になる額。 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |||
600m2<Ax≦900m2 | 0円 | 80,000円。ただし、(Ax-300m2)×300円+100,000円+80,000円>280,000円のときは(Ax-300m2)×300円+100,000円に加算した額が280,000円になる額。 | 80,000円 | 80,000円 | |||
900m2<Ax≦1,200m2 | 0円 | 0円 | 80,000円。ただし、(Ax-300m2)×300円+100,000円+80,000円>370,000円のときは(Ax-300m2)×300円+100,000円に加算した額が370,000円になる額。 | 80,000円 | |||
1,200m2<Ax | 0円 | 0円 | 0円 | 80,000円。ただし、(Ax-300m2)×300円+100,000円+80,000円>460,000円のときは(Ax-300m2)×300円+100,000円に加算した額が460,000円になる額。 | |||
備考 1 受益者負担金は、一画地ごとに算定する。一画地とは、地形や現実の利用状況等からみて一体をなしていると認められる範囲をいう。隣接する2筆以上の土地(所有者が違う場合を含む)がある場合には、それらを合わせた範囲を一画地とし、その反対に一筆の土地であっても区分して賦課する必要がある場合には、それぞれを一画地とすることができる。 2 受益者負担金の額は、③で算定した額(100円未満切捨て)と④で算定した額(100円未満切捨て)との合計額とする。 3 一画地の土地面積をAとする。 4 住宅及び事業所の場合、事業所面積率をx住居面積率をyとする。
(事業所床面積B/(事業所床面積B+住居床面積C))=事業所面積率=x(小数第1位未満切捨て) (住居床面積C/(事業所床面積B+住居床面積C))=住居面積率=y(小数第1位未満切上) 5 事業所面積率が50パーセント未満の場合は、専用住宅として算定する。 | |||||||
5 1の表から4の表までに定める区域以外の区域
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 負担金の額 |
第5負担区 | 508円 | 当該受益者が基準日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、第5条の規定により公告された区域内に存するものの面積に左記の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額。ただし、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。 |